ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)(愛称:スマイル・ジャパン)
経済危機からの復活例・・・第一次石油危機
日本の戦後史に残る経済危機のひとつに、1973年の第1次石油危機があります。原油価格がほぼ4倍に急騰し、インフレ率(消費者物価指数上昇率)は20%を超えて「狂乱物価」と呼ばれた、深刻な事態でした。
第1次石油危機は、結果的に日本の高度成長をストップさせる歴史的転機となりました。原油をほぼ全量輸入に頼る日本の将来に対する悲観論が強まり、日経平均はほぼ2年間にわたり下落傾向となりました。
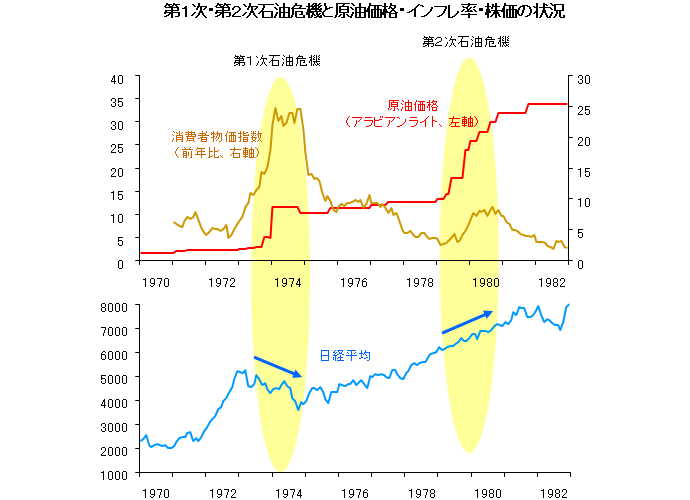
(出所)総務省資料、資源エネルギー庁資料、ブルームバーグよりSBIファンドバンク作成
しかし悲観論とは裏腹に、その後の日本は見事に立ち直り、物価は安定化、株価は長期の上昇トレンドへと転換しました。1979年には再び第2次石油危機が到来しましたが、このときは日本経済は予想以上の抵抗力を示し、株価は上昇傾向を続けました。
その背景には、危機の後に日本企業が見せたすばらしい適応力がありました。
日本企業は、省エネに向けた製造工程の見直し、合理化、技術開発等を進め、より少ないエネルギーでより多くの生産を可能にしていきました。下図のエネルギー原単位(1単位の製造業生産に必要なエネルギー量)の大幅低下がそれを如実に表しています。
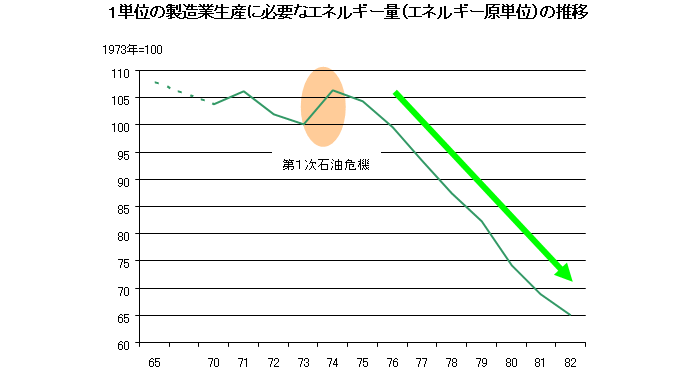
(出所)(財)省エネルギーセンター「エネルギー・経済統計要覧」よりSBIファンドバンク作成
この体質強化の結果、再び訪れた第2次石油危機の時には、日本経済は諸外国が羨むほどの強靭さを発揮しました。現在でも定評のある日本企業の省エネ技術等における優位性は、この頃から受け継がれてきたといえます。
大地震後の株式市場・・・関東大震災と阪神・淡路大震災
甚大な被害を及ぼした過去の巨大地震の後の株価をみると、1923年の関東大震災ではおよそ10ヵ月後、1995年の阪神・淡路大震災では6ヵ月後に株価は底打ちしています。
災害からの復興期待が株式市場にも反映されてくるものと考えられます。
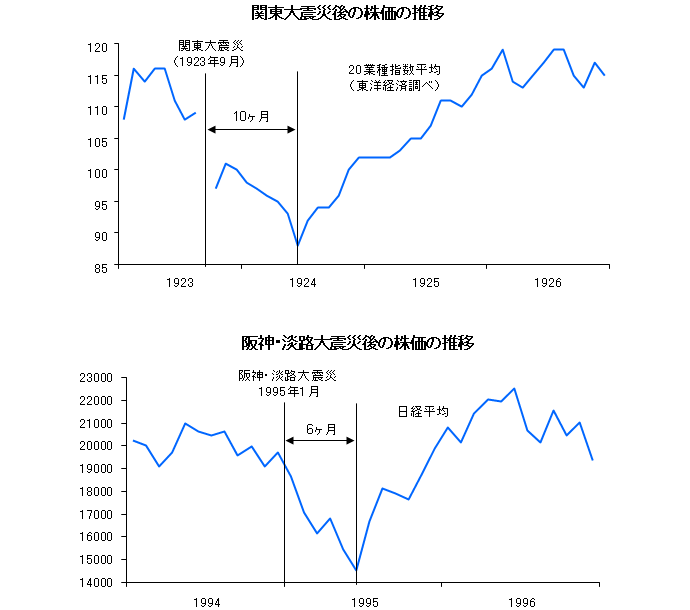
(出所)ブルームバーグ等よりSBIファンドバンク作成
原発事故後の株式市場・・・「チェルノブイリ」とDAX指数
1986年にウクライナで発生したチェルノブイリ原発事故は、福島第1原発事故と同じく「レベル7」級の事故となりました。地理的に比較的近いドイツのDAX指数は、約3ヶ月にわたり17%程度下落しましたが、その後持ち直しています。
株式市場の方向を決めるのは、基本的には経済情勢・企業業績であり、原発事故が制御されている限り株価回復の阻害要因にはならないものと考えられます。
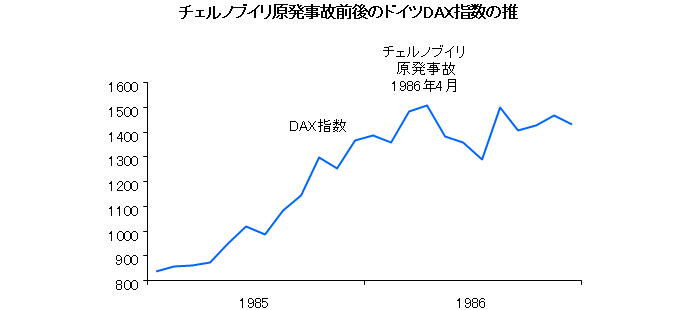
(出所)ブルームバーグ等よりSBIファンドバンク作成