※2014/10/15現在
![]() アメリカ合衆国のご紹介
アメリカ合衆国のご紹介

|
|
歴史と政治
年月 |
略史 |
|---|---|
1492年 | コロンブスがカリブ海の島に上陸 |
1640年 | 英国がニューイングランド等に植民地を建設 |
1776年 | 7月4日に独立宣言 |
1848年 | カリフォルニアで金発見 |
1861年 | 南北戦争が勃発 |
1867年 | ロシアからアラスカを購入 |
1898年 | スペイン・アメリカ戦争(キューバ、フィリピン、プエルトリコ、グアム等を勢力圏に) |
1917年 | 第一次世界大戦に参戦 |
1929年 | 株価大暴落 |
1933年 | フランクリン・D・ルーズベルト大統領就任 |
1941年 | 日本が真珠湾攻撃。米国も第二次世界大戦に参戦 |
1948年 | マーシャル・プランへの資金提供を決定 |
1949年 | 北大西洋条約機構(NATO)締結 |
1950年 | 朝鮮戦争勃発 |
1957年 | スプートニク・ショック |
1963年 | ケネディ大統領暗殺 |
1964年 | トンキン湾決議。ベトナム戦争へ |
1969年 | 7月20日に、アポロ11号が人類初の月面着陸 |
1975年 | サイゴンが陥落し、ベトナム戦争が終結 |
1981年 | レーガン大統領の時代(〜89年) |
1990年 | クウェートをイラクが侵攻。湾岸戦争へ |
2001年 | 9月11日に同時多発テロが発生 |
2009年 | アフリカ系で初のオバマ大統領が就任 |
アメリカ経済の概況
アメリカ合衆国は、世界の政治・経済を牽引する「超大国」です。主に英国を出身地とする人々により建国されましたが、ドイツ、イタリア、アイルランドなど、その他多くの欧州諸国からの移民も少なくありません。近年はラテン・アメリカからの移民が増えており、過去10年間における人口増加数(2,732万人)の43%が同地域の人々で占められています。2010年の名目GDPは14兆6,578億ドル(IMF調べ・1ドル79円換算で約1,158兆円)で、第2位の中国(同5兆8,783億ドル)を大きく引き離しています。
アメリカは、近年3度の「大戦」に勝利することで、指導的な地位を構築してきました。第一次世界大戦、第二次世界大戦、冷戦がそれに該当します。その結果、1960年、1980年、2000年まで20年ごとに、実質GDPの金額はそれぞれ2.4倍、2.1倍、1.9倍と拡大してきました。そして、その通貨である「ドル」は、世界の基軸通貨として、世界中のあらゆる場面で、主要な決済手段や価値貯蔵手段として用いられています。
こうした中、21世紀を迎えたアメリカですが、2001年の同時多発テロ、2008年のリーマン・ショックなど、多くの試練に直面することになりました。2010年までの過去10年間、実質GDPの成長率は累計で18%であり、これまでの拡大ピッチから減速しているようにみられます。下の表にもみられる通り、米国のGDPについて、その約7割が個人消費となっていますが、それに大きな影響を及ぼす雇用や住宅市況等が米国経済の大きなポイントになります。
(表)米国の実質GDP推移とその内訳
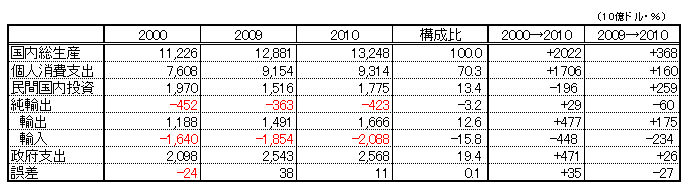
- ※米商務省データよりSBI証券が作成
住宅バブルの形成・崩壊と米国経済
サブプライムローンは、信用度の低い人向けの住宅ローンです。(1) ローン組成後数年間は、元利金の返済が低めに抑えられたことから、所得の低い人でも組めたこと、(2) 住宅ローン債権は証券化され、投資家に転売されたことから、金融機関が資金回収を早期化でき、リスクを抑えられたこと、(3) 米国で住宅価格の上昇が長期化し、多くの場合は、住宅の転売で利益が出て返済ができたこと、等を背景に、米国で急速に普及することになりました。ちなみに、多くのサブプライムローンは、担保に供している住宅の価格が上昇すると、その分融資枠が増える仕組みでしたので、住宅価格の上昇は消費の拡大に寄与しました。
米国の住宅価格は2006年4月までの10年間で3倍弱(S&P/ケース・シラー住宅価格指数・主要10都市)になりました。特に「ITバブル」後の景気後退を防ぐべく政策金利が引き下げられた(2001年1月〜2004年5月)ことが、住宅バブルを助長させました。2006年までの4年間、個人消費は年平均で3.3%増加し、実質GDPも同3.0%成長しました。同様に2004年〜2006年、雇用者数は月平均で18万3千人増加しました。米国経済はまさに絶好調であったと言えます。
しかし、2004年5月〜2006年6月の金融引き締めを契機に、住宅価格は2006年4月に天井となりました。その後は2009年4月の底値まで、同価格は33%弱の値下がりとなっています。その結果、もともと返済能力に限界のあった消費者の間で債務不履行や差し押さえが増え、それが米国の金融システムを圧迫するようになりました。その結果、5兆ドルの住宅ローン債権を抱えていたと指摘される政府系の住宅金融機関(GSM)が経営危機に陥り、ついには投資銀行大手のリーマン・ブラザーズが破綻するという事態(2008年9月 リーマン・ショック)に発展しました。
その後、FRB(米連邦準備制度理事会)による金融緩和や政府の緊急経済対策(2009年2月 米国再生再投資法)を経て、米国経済は金融危機の淵から脱出することになります。ただ、現在でも雇用の回復は緩慢であり、住宅価格もピークから3割超さがった水準で低迷しています。このため、米国経済がリーマン前の輝きを取り戻すのは難しいとの見方も出ています。
(図)米住宅価格と消費  |
(図)米雇用情勢と消費  |
- ※Bloomberg、米労働省データ等をもとにSBI証券が作成。「ケースシラー10都市」はS&P/ケースシラー住宅価格指数のうち主要10都市の価格を指数化したもの。
消費財を中心に毎年貿易赤字を計上
米国の貿易は基本的に輸入超過の構造になっています。コンピュータや半導体を発明した国であるとともに、広大な農作地を擁し、資本財や食料品・飲料については輸出超過の傾向です。しかし、消費財や工業用原料は輸入超過で、特に米国景気が消費主導で拡大している時ほど、その超過額は大きくなりがちです。
前項の図にもある通り、住宅価格の上昇や雇用の拡大を背景に、米国の消費(小売売上高)は2007年11月のピークまで拡大を続けました。それと併せるかのように、米国の輸入超過額も2006年まで拡大傾向を続け(下図)、特に2005〜06年には年間7千億ドル規模(1ドル79円換算で約55兆3千億円)にのぼっています。国別には、かつては、日本に対する輸入超過(貿易赤字)が政治問題にまでなりましたが、近年は中国向けが圧倒的(下表)に多くなっています。
一般的に、貿易赤字・経常赤字の計上は、その国の通貨にとっては下落要因になります。特に貿易赤字・経常赤字が巨額な場合は、その国の通貨不安につながるケースもあります。しかし、米国の場合は自国通貨が世界の基軸通貨であるドルであるため、その分、急激な下落を免れていると考えられます。米国との貿易でドルを手にした外国の多くは、米国への証券投資等を通じ、米国へドルを還流させています。1995年以降、米国は「強いドル」を基本政策のひとつとしてきましたが、これは、ドル資産の価値安定を強調することで、米国へのドル還流をうながし、貿易・経常赤字とのバランスを図ることが狙いであると考えることができます。
米国との貿易でドルを稼いだ国の多くも、既述のサブプライムローンに代表される資産担保証券等の米国資産を購入していました。このため、リーマンショックは時を置かずして、世界の金融危機として伝播してしまいました。これは見方を変えれば、米国による「強いドル」政策の限界が露呈してしまったと言えます。これを受け、米国のオバマ政権は2010年、5年間で輸出を2倍に拡大させることを基本戦略に据えました。米国にとっても貿易・経常赤字の積み増しは不健全であることに変わりないと考えられます。
(図)米国「純輸出」の推移(10億ドル) 
|
(表)2010年/米国の地域別貿易収支(億ドル) 
|
巨額の財政出動もあり財政赤字が拡大
米国の財政収支は、IT景気拡大に沸いた一時期を除き概ね赤字が続いています。特にリーマンショック後の2009〜10年は、オバマ政権になって成立(2009年2月)した「米国再生・再投資法(The American Recovery and Reinvestment Act of 2009/再生法)」による減税・財政支出拡大の影響もあり、年1兆6千億ドル規模(1ドル79円換算で約126兆4千億円)の赤字となりました。
「再生法」は、総額7,872億ドル(同上換算で約62兆2千億円)にのぼる経済対策で、減税のみならず、エネルギー・環境政策にも多額の予算を配分していることから「グリーン・ニューディール」との異名も持ちます。これにより2009年末で200万人、2010年末で300万人の雇用を創出することが大きな目標となりました。
こうしたオバマ政権自体の経済対策に加え、富裕層への減税を含む「ブッシュ減税」の2年延長もあり、当面の財政赤字額が大きい数字になっています。2011年5月16日には、米連邦政府の債務残高が法廷上限の14兆2,940億ドル(同上換算で1,129兆円)に達したため、オバマ大統領は同上限を引き上げようと図りましたが、野党共和党との合意に手間取りました。結局、2011年8月、10年間で歳出を2兆4千億ドル削減することを条件に、この債務上限は2兆1千億ドル引き上げられることになりました。
なお、残念なことに、主要格付け機関のひとつであるS&P(スタンダード&プアーズ)は8月5日、米国の長期債格付けをそれまでのAAAからAA+に引き下げました。無論、極端な財政不安を懸念すべき格付けではありませんが、基軸通貨を有する米国の国債が最上位から落ちたことは、今後、投資家に微妙な影響を与えてくる可能性があります。
(図)米国財政収支の推移(10億ドル)
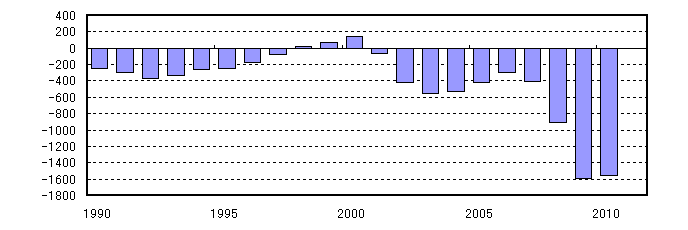
- ※米労働省データをもとにSBI証券が作成。
雇用の改善が政府・FRBの重要課題
米国でもっとも重要な指標のひとつが、労働省により発表される雇用統計です。一般的に、雇用関連指標自体は、景気の遅行指標的な側面が強いですが、米国の場合、この統計が基本的に次月最初の金曜日に発表されるため、「前月の経済実態を月内で原則最も早く示唆する経済指標」として、市場から高い注目を集めます。雇用統計の中にもいくつか指標がありますが、そのうちで最も重要なのが「非農業部門雇用者数増減」と「失業率」です。
このうち、前者(農業部門は景気変動の影響を反映しにくいため除外)については、リーマンショック直後の2009年1月に前年比で82万人も減少し、過去50年間で最悪の減少となりました。その後、再生法の実施や、減税の延長、世界的な金融システム安定化の取り組みもあり、一時は前月比46万人弱回復する局面もありましたが、2011年・上半期は月平均12.6万人増と、過去50年間の平均(同12.8万人)並みの増加になっています。なお、失業率については2009年10月の10.1%を底に、そこからやや回復した水準での推移になっています。
雇用の安定は、オバマ大統領に限らず、政権にとっては支持率に直結する重要な課題です。また、それは中央銀行であるFRBにとっても同様です。2011年の半ばに入り、雇用回復に一巡感が出始めていますが、リーマンショックを経て、企業が雇用に慎重になり始めていることを示唆している可能性もあります。雇用に不安定感が残る間、FRBは金融の引き締めに動きにくい可能性もあり、要注目の経済指標と言えます。
(図)米農業部門雇用者数増減(前月比・千人)  |
(図)米失業率(%)  |
- ※Bloomberg、米労働省データをもとにSBI証券が作成。
人口減少・名目成長率マイナスの日本、人口増加・名目成長率プラスの米国
(図)米国の人口と名目GDP推移
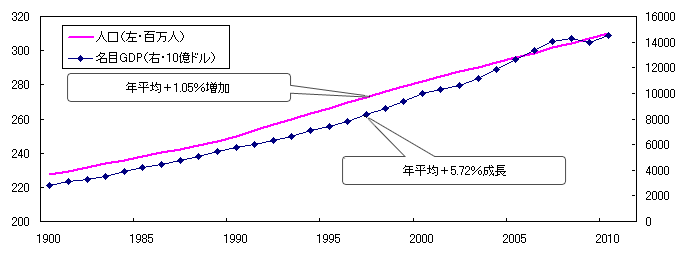
- ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。
長期にわたり、世界一の経済大国・軍事大国として、あるいは「西側自由主義経済諸国」のリーダーとして君臨してきた米国には、古くは欧州・アジアから、現在ではラテン・アメリカ諸国から多くの人々が「移民」として流入してきました。現在でもその流れは続いており、米国は先進国では数少ない人口増加国になっています。平均人口増加率は過去50年で年1%超となっています。経済成長の要因が「人口の増加」「設備の増加」「技術発展」であるならば、米国はそのための重要なファクターをしっかりと抱えていると考えられます。
ちなみに、15歳未満の人口が占める比率(2014年・米国勢調査局推定)は20.1%で、日本12.5%、英国17.3%、ドイツ13.0
%等の先進国と比べて高く、将来を担う若者が比較的多いというのは心強い材料と考えられます。65歳超の人口が占める比率は14.1%で日本25.4%、英国17.5%、ドイツ21.1%に比べて小さく、老齢化の進展も遅めといえましょう。
人口が着実に増大していることに加え、技術開発の面でも世界をリードする米国。そんな同国の過去50年間における名目経済成長率は年平均5.72%となっています。この点は、人口が減少に転じ、名目経済成長率がマイナス傾向となってきた日本経済と、本質的に異なる点と理解すべきかもしれません。