※2014/10/15現在
![]() メキシコ合衆国の紹介
メキシコ合衆国の紹介
 |
|
歴史と政治
年月 |
略史 |
|---|---|
14世紀 |
アステカ文明が興り、栄える |
1519年 |
エルナン・コルテスの率いるスペイン人が侵入 |
1810年 |
メキシコ独立運動の開始 |
1821年 |
スペインより独立 |
1846年 |
米墨戦争(〜1848年。カリフォルニア他、国土の半分近くを米国に割譲) |
1910年 |
メキシコ革命勃発 |
1917年 |
現行憲法公布 |
1938年 |
石油産業の国有化 |
1982年 |
債務危機発生 |
1986年 |
GATT(関税及び貿易に関する一般協定)加盟 |
1993年 |
APEC(アジア太平洋経済協力会議)参加 |
1994年 |
北米自由貿易協定(NAFTA)発効、OECD加盟、通貨危機発生 |
2000年 |
フォックス大統領就任(70年以上続いた制度的革命党政権の終焉) |
2006年 |
カルデロン大統領就任(第65代大統領) |
基本的な特徴
メキシコ合衆国は、アメリカ合衆国(以下「米国」)の南に隣接している、大きな国(面積は日本の5.2倍)です。米国が、英国を中心とする西ヨーロッパの人々により建国され、宗教的にもプロテスタント諸派が多数派であるのに対し、メキシコは、スペイン人等のヨーロッパ人と先住民の混血が主流で、宗教的にはカトリックが中心です。ラテン・アメリカの一角を形成する国として、米国とはかなり異なる特徴を有しています。
ただし、メキシコは米国と3,000キロメートルを超える国境を有しており、同国との政治的・経済的関係は密接です。近年、メキシコ大統領は例外なく、米国の大学を卒業したテクノクラート(高度な専門知識を有した行政官や官僚)によって占められ、米国の指導者層と近い価値観を有しているとみられます。また、メキシコからの輸出の8割は米国向けで、米国への経済的依存度は大きいとみられます。さらに、年間約200億ドル前後にものぼる米国移民からの送金も、メキシコ経済を強く支えていると考えられます。
メキシコ経済の強み
【メキシコと米国の実質GDP成長率(四半期・前年同期比・%)】
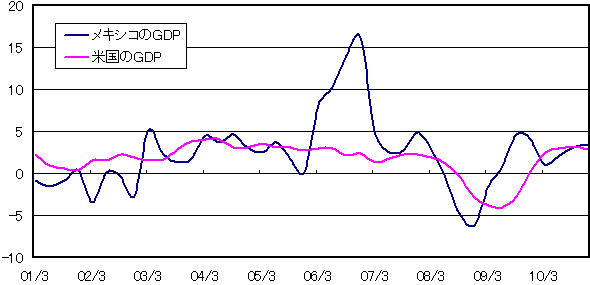
- ※BloombergのデータをもとにSBI証券が作成
メキシコの実質GDPは2010年までの過去10年、平均(四半期・前年同期比)2.4%と堅実な成長を遂げました。
同時期に平均1.7%の成長であった米国と比べると高い成長を遂げてきました。特筆されるのは、過去5年間の平均成長率が米国は+1.0%に対し、メキシコは+3.6%(四半期データの平均)と特に高くなっていることです。米国経済への依存度が大きいメキシコ経済ですが、成長率では米国を上回って推移していることになります。
メキシコのGDPを支出面で区分すると、その7割弱(2010年)が民間最終消費となっています。これに大きな影響を与えるのは雇用とみられますが、メキシコの失業率は足元5%台で推移しており、9%割れ水準の米国のみならず、ブラジル(6%台)やチリ(7%台)等の主要南米諸国と比べても低くなっています。こうした低い失業率が家計消費の堅調に一役買っていると考えられます。
|
メキシコ経済において、輸出がGDPに占める比率は32.5%(2010年)で、BRICsの一角を占めるブラジルの11.1%(同)と比較しても高めになっています。 特に、輸出額全体に占める米国向け比率は約8割となっており、米国経済の発展を素直に享受出来る状況と言えます。逆に米国経済が減速・後退する時、メキシコはその悪影響を直接受けやすい構造と言えるでしょう。 なお、産業別の輸出構成比としては、全体の8割強が製造業となっており、特に自動車や同・部品、電気・電子機器等が代表的な製品となっております。世界有数の生産量を誇る原油も主力輸出商品であることに変わりありませんが、確認埋蔵量の減少等もあり、その重要性は低下傾向にあります。 |
メキシコの支出別GDP構成(兆ペソ) 
メキシコの産業別輸出構成比(%) 
|
|
官民による積極的なインフラ(社会資本)投資は、総固定資本形成の増加により経済成長に寄与するだけでなく、生産拠点としてのメキシコの競争力を高めてゆくと期待されます。 2000年から2006年までの社会資本投資予算は、対GDP比で年平均3.48%で推移してきました。2007年から2010年にはさらに、同4.57%へ増加した模様です。 そのための資金調達手段として中核的な役割を果たしているのが、国家インフラ投資ファンドです。同ファンドを用いたインフラ投資は2007年には100億ペソ規模でしたが、2010年には、451億ペソ規模へ拡大し、2011年は647億ペソ前後の投資が見込まれています。 なお、三井物産や住友商事、丸紅、三菱商事といった日本の総合商社は、LNG(液化天然ガス)ターミナルや、下水道処理等の構築・管理等、メキシコのインフラ投資に関わっています。 |
メキシコのインフラ投資(10億ペソ) 
|
|
メキシコの財政収支は、2010年対GDP比で4.4%の赤字となっています。この数字はコロンビア、チリといった南米諸国と同程度になります。また、債務残高がGDPに占める比率は同年42.7%で、ブラジルの66.1%、アルゼンチンの47.9%と比べると低い数字(いずれもIMFデータ)になっています。メキシコ財政について、他国と比較する限り、大きな問題はないように見受けられます。 ただ、公的部門の収入の3割を原油関連が占めていること、メキシコの原油埋蔵量が減少傾向にあることを考慮すると、課題が残るとみられます。 幸い、2009年に承認された税制改革により、徴税対象者数は増加傾向になっています。公的部門全体の債務はGDP比で32%(2010年)となっていますが、2015年には28%台に低下すると期待(メキシコ大使館資料)されています。 |
メキシコの財政収支対GDP比(%) 
|
メキシコ経済の現状
|
メキシコの輸出と鉱工業生産  |
メキシコの輸出と雇用情勢  |
- BloombergのデータをもとにSBI証券が作成。
冒頭でご紹介した通り、メキシコは米国向けの自動車・電子機器の輸出拠点であり、輸出の8割が同国向けで占められています。このため、グラフにもありますように、メキシコの鉱工業生産は、その輸出額と強い相関関係を有しています。
リーマン・ショック(2008年9月)以後、米国経済は、個人消費の強弱を示す小売売上高が2009年3月を底に回復し、2009年11月以降は前年同月比でも増加に転じました。メキシコの輸出額も同月に前年同月比増加に転換し、鉱工業生産は12月から同プラスに転じています。米国経済は、住宅価格に弱さが残るものの、企業業績、雇用、消費は回復傾向が続いていますので、メキシコの生産・輸出も追い風を受けているとみられます。
なお、メキシコの雇用については生産・輸出の底入れから半年程度遅れ、2010年9月に底入れとなり、その後は概ね回復傾向となっています。
|
海外からメキシコへの送金額と小売売上高  |
消費者信頼感指数と小売売上高  |
- BloombergのデータをもとにSBI証券が作成。
- (消費者信頼感指数は2003年1月を100とする指数であり、単位はありません)
2010年の米国国勢調査では、同年における米国の全人口約3億人に占めるヒスパニック(メキシコを中心とする中南米出身の人々)の人口は約5千万人で構成比は16%になっています。また、同年までの過去10年間に、米国の人口は約2,700万人(9.7%)増えましたが、増加分の56%は、これらヒスパニック系の人々の人口増によるものとなっています。
合法・不法を併せ、メキシコから世界一の経済大国である米国へ移住する人々は多く、彼らが本国の家族へ送るお金は、月平均17.7億ドル(2010年)と、メキシコ経済にとっても無視できない規模となっています。
既にご紹介した製品や商品の輸出のみならず、個人のお金も国境をまたいで動いてる訳で、メキシコと米国の結び付きは想像以上に強いと言うことができるでしょう。
米国からの送金が前年同月比で36%も減少した2009年10月、メキシコの消費者信頼感指数も底を付けました。当時、同国の小売売上高は前年同月比で減少傾向にありましたが、2010年以降は毎月(情報更新日現在)増加傾向になっています。
一方、国内の失業率についても2009年9月の6.4%が天井で、2011年3月には5%割れ水準まで改善しておりますので、そのこともメキシコの消費を押し上げているとみられます。
|
メキシコの消費者物価上昇率(前年同月比)  |
メキシコの金利動向(%)  |
- BloombergのデータをもとにSBI証券が作成。
メキシコは、インフレ率を一定の範囲内に抑えることを意図した目標値(インフレ目標)を採用しています。具体的には、消費者物価を3%±1%の枠内に抑えるべく、中央銀行は金融政策を展開することになります。
現在、メキシコのインフレ率はこうした目標値近辺で推移しておりますので、金融政策を変更する理由は乏しいとみられます。メキシコの政策金利は2009年7月末以降、4.5%に据え置かれています。
グラフでも確認できますように、物価上昇率そのものが減速しています。そのこと自体がインフレ目標値設定の効果と考えることも出来ますが、「米国への輸出拠点」として、アジアと比較すると人件費が高いことから、賃金インフレが生じにくいという面も指摘されます。それでも、世界的な原材料・食料品価格の上昇が今後、物価上昇を加速させる可能性も指摘されています。
メキシコ経済の先行きとメキシコ・ペソ
メキシコ主要経済指標の推移
項目 |
西暦 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質GDP成長率(%) |
-6.1 |
5.5 |
4.6 |
4.0 |
3.4 |
3.2 |
3.2 |
|
名目GDP(10億ドル) |
882 |
1,039 |
1,167 |
1,232 |
1,293 |
1,356 |
1,428 |
|
一人当たり名目GDP |
8,203 |
9,566 |
10,638 |
11,115 |
11,556 |
11,995 |
12,504 |
|
年平均消費者物価(%) |
5.3 |
4.2 |
3.6 |
3.1 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
失業率 |
5.5 |
5.4 |
4.5 |
3.9 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
人口(百万人) |
107.6 |
108.6 |
109.7 |
110.8 |
111.9 |
113.0 |
114.2 |
|
一般政府債務(GDP比・%) |
44.6 |
42.7 |
42.3 |
42.1 |
42.0 |
41.9 |
41.6 |
|
経常収支(GDP比・%) |
-0.71 |
-0.55 |
-0.90 |
-1.09 |
-1.32 |
-1.29 |
-1.38 |
|
- IMF(国際通貨基金)の「2011年4月・世界経済見通し」をもとにSBI証券が作成。2011年以降はIMFの予想。
米国への依存度が強いメキシコ経済は、リーマン・ショックの影響を受け、2009年にはマイナス成長に陥りました、しかし、それ以降は、米国経済の拡大が追い風となり、回復傾向を強めています。IMF(国際通貨基金)では、2011年以降も当面、メキシコの実質GDPは3〜4%台の成長を遂げ、失業率も低下してゆくと予想しています。物価も安定が見込まれており、メキシコ経済は総じて良好な状況が続くと見込まれています。ちなみに、2011年2月に、メキシコのフェラリ経済相が来日した折、日本のメディアに語った成長率見通しも、IMFの予想と傾向は同じとみてよいでしょう。
ただし、米国においては、企業から雇用に対する消極姿勢が解消したわけではない上、住宅価格は足元、弱めで推移しています。これらの問題はメキシコから米国へ移住した人々の生活に悪影響が想定され、それらの人々からメキシコ本国への送金に逆風となる可能性があります。また、米国への製品・商品の輸出拠点として、今後もアジア企業と厳しい競争が想定され、消費者の賃金上昇にブレーキがかかる懸念が残ります。
こうした中、メキシコ政府は、航空機部品など新たな産業分野の集積に取り組む一方、総額3,300億ドル(2007年から12年まで)のインフラ投資を推進しており、国際競争力の維持・向上に努めています。
|
メキシコ・ペソとドル・円(月足)  |
メキシコ・ペソと米雇用統計(月足)  |
- BloombergのデータをもとにSBI証券が作成。
メキシコの通貨はメキシコ・ペソです。対ドル・対円の外為相場はグラフの通りで、過去10年間という期間でみると、ドル及び円に対し、下げています。メキシコの経済成長率は他の新興国に比べれば緩やかであり、かつ、インフレ率の低下もあって金利が低下傾向にあったことが要因とみられます。ただし、米国経済が底入れし、メキシコ経済に追い風が吹き始めた2009年1月以降は、反発局面にあります。
2008年末から2011年5月13日までのメキシコ・ペソ相場の騰落率をみると、対ドル、対ユーロ、対円の順に上昇率が大きくなっています。反面、ブラジル・レアルや豪ドルに対しては下落しています。先進国と新興国の中間的なポジションにいるメキシコ経済ですが、通貨にもそうした特徴が表れていると言えるかもしれません。
これまでご紹介してきた通り、メキシコ経済は米国経済と連動しているとみられますが、変動率はメキシコ経済の方が大きくなりやすいと言えます。このため、米国経済が成長する局面では、メキシコ経済の成長率がより大きくなりやすく、メキシコ・ペソは対ドルで買われやすくなると考えられます。即ち、グラフからもご理解頂けるように、ペソの対ドル相場は米国の雇用情勢と連動する傾向が強いと言えます。
なお、メキシコには、トヨタ、日産、ホンダといった我が国の自動車大手やパナソニックなどの電機大手も、米国向けの生産・輸出拠点として進出しています。米国経済への依存度が大きいという意味では、メキシコと日本には共通点も多いと言えるでしょう。