※2014/10/15現在
![]() オーストラリア連邦のご紹介
オーストラリア連邦のご紹介
概略

|
|
歴史と政治
年月 |
略史 |
|---|---|
1770年 | 英国人探検隊クックがシドニー近郊に上陸。英国領有宣言。 |
1788年 | 英国人フィリップ海軍大佐一行が入植開始。初代総督に就任。 |
1901年 | 豪州連邦が成立。 |
1942年 | 英国議会から独立した立法権を取得。 |
1986年 | 英国から司法上の完全独立を達成。 |
2000年9月 | シドニー五輪開催。 |
2007年11月 | ラッド氏率いる労働党がハラード氏らの保守連合を破り政権を奪取。 |
2010年6月 | ジュリア・ギラード氏(労働党)が初の女性首相に就任。 |
- ※外務省、JETROのデータをもとにSBI証券が作成
経済の概況
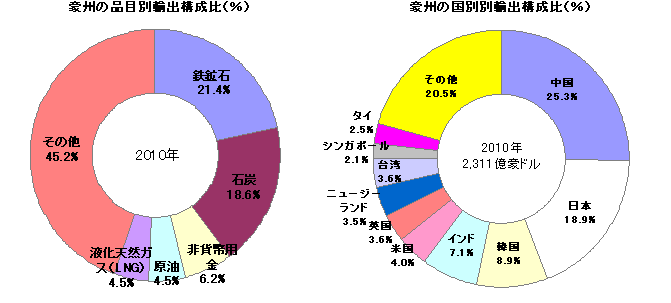
- ※JETROのデータをもとにSBI証券が作成(小数点以下は四捨五入)
米内務省・地質調査所「MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2011」によると、豪州の金生産量シェアは、世界の約10%で第2位にとどまっていますが、埋蔵量シェアは約14%で第1位となっています。この他、鉄鉱石や石炭でも世界有数の生産量及び埋蔵量を有しています。これらに原油、天然ガス他を加えた諸資源の豪州輸出高に占める比率は計50%を超えており、同国は紛れもなく「資源大国」と呼ぶに相応しいポジションを獲得していると考えられます。
なお、輸出相手国先別の構成比(ジェトロ・2010年)は、中国25%、日本19%、韓国9%、インド7%他となっています。人口増加率の面でも経済の面でも発展著しいアジアを「得意先」としていることも、豪州経済のメリットといえましょう。
高い債券利回り
国名 |
10年国債(%) |
2年国債(%) |
Moody's |
S&P |
政策金利(%) |
|---|---|---|---|---|---|
日本 |
0.96 |
0.11 |
Aa3 |
AA- |
0.10 |
米国 |
2.04 |
0.31 |
Aaa |
AA+ |
0.25 |
英国 |
2.16 |
0.42 |
Aaa |
AAA |
0.50 |
ドイツ |
1.74 |
0.14 |
Aaa |
AAA |
1.00 |
フランス |
2.99 |
0.56 |
Aaa |
AA+ |
1.00 |
豪州 |
3.88 |
3.27 |
Aaa |
AAA |
4.25 |
カナダ |
2.07 |
1.24 |
Aaa |
AAA |
1.00 |
イタリア |
5.45 |
3.22 |
A3 |
BBB+ |
1.00 |
ベルギー |
3.43 |
1.26 |
Aa3 |
AA |
1.00 |
オランダ |
2.30 |
0.35 |
Aaa |
AAA |
1.00 |
- ※BloombergのデータをもとにSBI証券が作成
- ※EU加盟国の政策金利はECB(欧州中央銀行)による。なお、日本、米国の政策金利は下限が0で、表は上限の金利。
- ※10年国債、2年国債、政策金利は年利回りで単位は%
- ※「Moody's」「S&P」は長期債務格付け
国名 |
成長率(%) |
|---|---|
日本 |
0.7 |
米国 |
1.6 |
英国 |
1.3 |
ドイツ |
1.0 |
フランス |
1.1 |
豪州 |
3.0 |
カナダ |
1.9 |
イタリア |
0.2 |
ベルギー |
1.5 |
オランダ |
1.3 |
- ※IMFのデータをもとにSBI証券が作成
- ※2001〜2010年の実質GDP成長率の平均(IMF推定を含む)
オーストラリアは、IMF(国際通貨基金)による分類では先進国に属しています。先進国でかつ、主要格付け機関による長期債務格付けがトリプルAクラスの国は概ね長期金利が3%台以下にとどまっています。そうした中、豪州の長期金利は年4%近くを維持しており、政策金利も相対的に高くなっています。
長期金利が、その国の成長性と期待インフレ率を織り込んでいると考えるならば、豪州は高い経済成長を期待されているとみることも可能です。別表にもある通り、確かに、豪州の経済成長率は、他の先進国よりも高めになっています。広大な国土と豊富な資源を有していることが豪州の特徴です。言い換えれば、先進国と資源国の性格を併せ持っていることが、豪州経済の成長要因になっていると考えられます。
通貨(豪ドル)
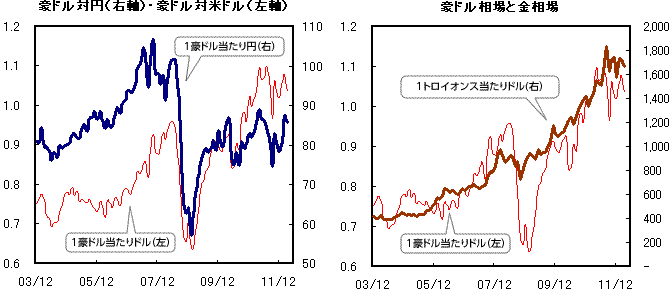
- ※BloombergのデータをもとにSBI証券が作成。データは2012年4月10日現在
- ※外為相場は、1豪ドル当たり米ドルまたは円。金スポット価格は1トロイオンス当たり米ドル
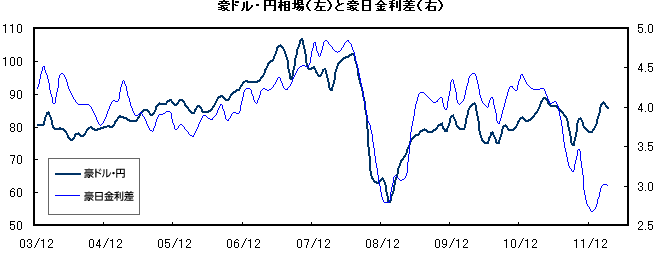
- ※BloombergのデータをもとにSBI証券が作成
- ※「豪日」金利差は、豪10年国債利回りから日本の10年国債利回りを差し引いた数字(%)で、拡大するほど豪ドル高になりやすい。
「1豪ドル当たり米ドル」相場と「金1トロイオンス当たり米ドル」相場は概ね同一方向に動く傾向が強くなっています。即ち、金価格の上昇は豪ドルの上昇要因で、金価格の下落はその逆であるとみることができます。豪州が世界一の金埋蔵量を有しているという事実が、こうした相関性の背景にある要因と考えられます。また、一般的に「金価格は米ドルと逆相関」にあるとみなされています。ドル自体の上昇力が弱いときは、金価格が上昇しやすくなるので、豪ドル相場も上昇しやすくなるという関係になっています。
なお「1豪ドル当たり円相場」を考える時は、上記の金価格の動向に加え、日豪2カ国の長期金利差も重要な要因になります。豪ドルの対円相場は、豪長期金利から日本の長期金利を差し引いた金利差が拡大するときに上昇しやすく、縮小するときに下落しやすい傾向があるためです。
最近の豪ドル相場の動きの特徴としては、金価格の高止まりを背景に、「1豪ドル当たり米ドル」相場が豪ドル高・米ドル安傾向で推移していることがあげられます。経済が回復途上の米国、重債務国問題を抱える欧州とも、緩和的金融政策を継続していますので、国際的な通貨システムそのものへの不安がくすぶっており、それが金価格へ追い風となっています。なお「1豪ドル当たり米ドル」相場の高止まりは「1豪ドル当たり円相場」でも、豪ドル高・円安要因ではありますが、豪日金利差が縮小している分、弱めになっています。
豪ドル相場と国際経済
新興国の経済発展を背景とする世界的な食料・資源価格の高騰は、世界経済における豪州経済のポジションを押し上げる要因とみられます。上記した通り、豪州は豊富な資源を有しているためで、その意味で、中長期的に豪ドルが持つポテンシャルは大きいとみられます。
なお、現在の世界経済で最も深刻な問題とみられる欧州重債務国問題は、過剰流動性を長期化させる要因になるとともに、安全資産としての金価格に追い風となるため、豪ドルにとっては追い風になる側面もあります。さらに欧州の人々が、同じ欧州系の人々による植民で建国された豪州に親近感を持ち、通貨分散の対象にする可能性も想定されます。
ただし、混乱が極端に拡大し、世界的な金融システムの混乱につながる場合は要注意です。リーマン・ショック(08年9月)をはさみ、豪ドルは対円で約3ヵ月で47%超も下げたという経緯があります。短期的かつ急激に、投資家のリスク許容度が縮小する時は大きくブレやすい通貨であるという側面にも配慮が必要でしょう。また、世界経済に先行して回復した豪ドル経済に対し、日本や米国の経済がキャッチアップする流れとなる場合も、日米と豪州の金利差縮小から豪ドル安をもたらすケースが想定されます。
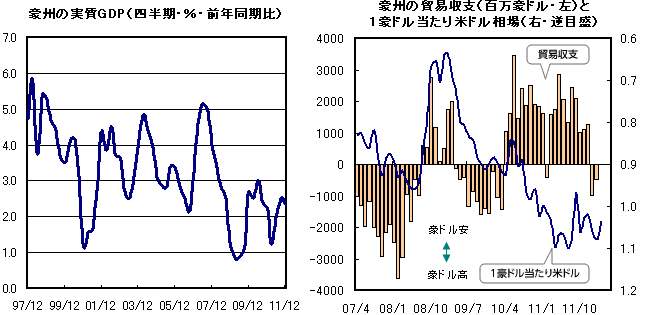
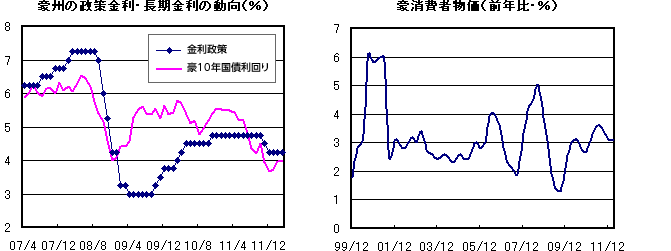
- ※Bloomberg、RBA(豪州準備銀行)、豪州統計局(ABS)よりSBI証券が作成
豪ドル経済の発展を期待した豪ドル相場の上昇が、豪州の輸出拡大にブレーキとなり始めています。また、最大の輸出相手国である中国経済が減速傾向をみせていることも向かい風になっています。このため、貿易収支が悪化の兆しを見せており、経済成長率も市場の期待を下回る傾向が出てきています。
このため、豪州準備銀行(RBA)は、2011年11月以降、金融緩和に転じています。インフレも一時に比べれば落ち着いてきていますので、豪州経済がさらに悪化した場合は、こうした緩和的金融政策が続く可能性があります。
ただし、豪州経済は「100年に一度」と称される資源ブームを背景に、先進国の中では高い成長率を維持しています。資源輸出のみならず、資源に絡んだ開発投資も旺盛なためです。今後も新興国の経済発展が続く限り、基本的には、豊富な資源を武器にした経済発展が可能であるとみられます。